|
|
|
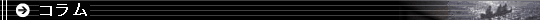 |
過去に掲載したコラムです。
■2003年9月8日
指揮者とオーケストラのコラボレーション(1)
(有)ソフィアート 代表取締役 竺原雅人
クラシック音楽に興味がある筆者にとって、オーケストラの指揮者、歌曲のaccompanistの存在はリーダーシップやマネジメントを考えるうえでの格好のモデルになります。今回と次回は、この視点から指揮者やオーケストラを通してコラボレーションについて考えたことを書いてみます。
20世紀後半の技術革新と工業化の進展は物質的豊かさをもたらすとともに地域的なハンディを次々と克服しました。そして、音楽の世界ではジェット機で世界を駆け巡るスーパースターの時代を招きました。こうしたなかで演奏会は、「感動を創造し共有する場、魂、感情がぶつかり合う場」から「ブランドの消費の場」へと次第に軸足を移して行ったように思われます。
こうしたなかで、かつてのオペラ劇場では当たり前に見られたこと、すなわち指揮者も歌手も一箇所にじっくりと腰をすえてアンサンブルを磨くという光景は過去のものとなりました。第一次大戦前は、北半球で演奏シーズンを終えたマエストロたちが何ヶ月もかけて南米に向かい、かの地の劇場で活躍しています。しかし、いまやスター指揮者やスター歌手が本番だけにやってきてはジェット機でさっと飛び去ってしまいます。リハーサルには参加することなく、おいしいところだけを取っていきます。最近では欧米の地方劇場も日本で引越し公演を行うことがありますが、そのプログラムを見ると、かつて一度も共演したことのない国際的スターが訪日公演のために出演するというものも見られます。ビッグネームなしの興行が難しいという事情ゆえですが、劇場が育んできたアンサンブル、演奏の伝統の力を示すのではなく、劇場が単なる伴奏者として、安く、便利な存在として利用されている(逆に利用している)のは残念です。
現実に多くの劇場では忙しさや予算の制約もあり、効率追求のために、コラボレーションとはいえないただの並行作業も見られます。
さて、ここからはオーケストラと指揮者とのコラボレーションを考える意味で、まず曲の音づくりに注目してみます。音といっても、①オーケストラが固有に持つ音、②指揮者独自の音色感、③特定の作曲家・曲自体が求める音に分けて捉えることができます。
①では、ビロードの音、栄光のフィラデルフィアサウンドとして知られるフィラデルフィア管弦楽団を挙げてみます。ある著名な指揮者が「同じ曲を同時期に振ったところ、ニューヨークやシカゴでは自分の音が出せたが、フィラデルフィアではどう振ってもフィラデルフィアの固有の音が出てきた」ということを述べた記事を読んだことがあります。
②については、古いところではクナパーツブッシュ、アンセルメ、ミンシュなどがその得意のレパートリーと結びついて彼らの音を形成しています。重厚な音を望む指揮者から軽やかな音づくりを望む指揮者までいろいろです。ドイツものからイタリア、フランスものまで曲のジャンルを超えた指揮者固有の音作りというところではカラヤンがその典型でしょう。
③についていえば、演奏の歴史、オーケストラの伝統そのものともいえますが、たとえばドレスデンとシューマン、ミュンヘンとワグナー、スカラ座とヴェルディといった地域的なつながりや演奏の伝統という関係をあげることができます。
演奏はこれらの要素がぶつかりあって実際の音が奏でられるわけですが、指揮者のリーダーシップのスタイルとオーケストラ(そしてコンサートマスター=リーダー)の主張の仕方次第でさまざまな展開が可能になります。
こうした点を踏まえて、次回ではコンサルティングや人材開発におけるコンサルタント/研修講師とお客様企業(研修の参加者)との関係について述べてみたいと思います。
|
| |
| |
